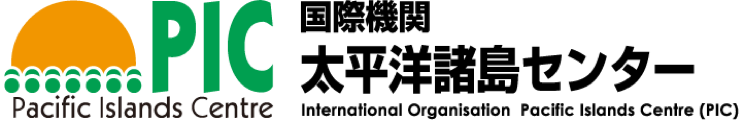フィジー 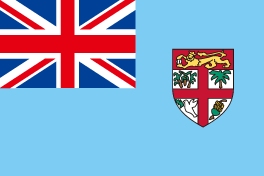
| 正式国名 | フィジー共和国(Republic of the Fiji Islands) |
|---|---|
| 人口 | 884,887人(2017年フィジー統計局) |
| 民族 | 先住民系(56.8%)、インド系(37.5%)、その他(5.7%) (Fiji Bureau of Statistics2007年データより算出) |
| 宗教 | キリスト教(64.9%)、ヒンズー教(27.7%)、イスラム教(6.3%) (Fiji Bureau of Statistics2007年データより算出) |
| 1人当りGDP | 5,589.39米ドル(世界銀行、2017年) |
| 電話の国番号 | (679)+(相手先の番号) |
| 面積 | 18,270k㎡ |
|---|---|
| 首都 | スバ(Suva) |
| 主要言語 | 英語(公用語)、フィジー語、ヒンディー語 |
| 政体 | 共和制 |
| 通貨 | フィジー・ドル |
フィジー共和国の主島ビチレブ島は、オーストラリアから北東に約3,100km、ニュージーランドの北2,100kmほどの位置にある。330余りの島々から成り、土地の総面積は四国とほぼ同じである。最も近い太平洋島嶼国のトンガは770km離れた東に、西のバヌアツは1,100km離れている。
太平洋で最も人気の高い観光地の一つであるフィジーは、質の高い旅行を求めるリゾート派から行動派のバックパッカーまで、すべての旅行者の要望に応えられる観光立国である。また、フィジーは太平洋島嶼国の中では2番目に大きな人口を持ち、地理的に太平洋島嶼国の中心に位置していることから、地域のハブ的な役割を担っている。このため、太平洋の国々と地域で構成される地域協力のための国際機関、太平洋諸島フォーラム(Pacific Islands Forum, PIF)事務局や南太平洋大学(USP)がフィジーに設置されている。
白砂のビーチ、青く澄んだサンゴの海、咲き乱れる山の花々といった豊かな自然と、メラネシア、ポリネシア、インドの文化が織りなす独特の魅力はフィジーだからこそ味わうことができる。
フィジーを訪れる人々は、透明度の高い海や洗練されたリゾート・ライフを満喫するだけでなく、南太平洋の国々に残る独自の伝統文化に出会えることを、その魅力のひとつにあげる。
主島のビチレブ島は東西146km、南北106kmで、その南東部に首都スバがあり、西部には観光の中心地ナンディとフィジー第1の空港ナンディ国際空港がある。スバとナンディはビチレブ島の南部を走る全長211kmの舗装道路クイーンズ・ロードと東側を走る全長265kmの一部未舗装のキングス・ロードで結ばれている。

●歴史(第二次世界大戦後)
1942年から43年にかけて、約8,000人のフィジー軍はアメリカとニュージーランドの指揮下に入り、ソロモン諸島で日本軍との戦闘に参加した。1970年10月10日、英連邦30番目の加盟国となり念願の独立を果たし、初代首相に故カミセセ・マラ(就任時は英国植民地政府の首席大臣)が就任した。1987年5月と9月に軍事クーデターが発生して共和制に移行し、国名をフィジー共和国に変更した。

●政治
フィジーは議員内閣制(一党制)をとっており、4年毎に実施される総選挙で与党となった政党の党首が首相に就任する。選挙制度は、全国を1選挙区とした非拘束名簿式比例代表制であり、2018年総選挙での議席数は51議席であった。国家元首である大統領(内閣他の助言によって公的権限を行使)は、議会において首相及び野党党首がそれぞれ候補者を1名指名し、議員による投票で選出される。
99年5月の総選挙でチョードリーが初のインド系首相に就任した。2000年5月、先住民系の権利擁護のためインド系政権の交替と97年憲法の廃止、マラ大統領の辞任等を主張する武装勢力が議会を占拠し、チョードリー首相ら閣僚30名を拘束する事件が発生した。同月バイニマラマ軍司令官が同事件の解決を図るべく行政権を掌握、戒厳令を発令し、97年憲法は政令により廃止された。7月、人質は解放され、イロイロ大統領、セニロリ副大統領が任命された。同月、ガラセ首相率いる暫定文民政権が発足した。11月、ラウトカ高等裁判所が暫定政権を違法とする判決を下し、2001年3月には控訴裁判所もこれを支持する判決を下した。同月、イロイロ、セニロリ正副大統領が再度任命され、ガラセ選挙管理内閣が発足。2001年8月には総選挙が行われ、ガラセ新政権が誕生した。以来2000年クーデターの事後処理等をめぐり、野党労働党との対立が続き、ガラセ首相とバイニマラマ司令官との確執も先鋭化していった。2006年3月、ガラセ首相は議会を解散、総選挙に踏み切り、与党統一フィジー党が再び過半数の議席を得て首相に再任され、労働党との連立政権を組織した。しかし、同年12月、バイニマラマ軍司令官はガラセ政権の腐敗粛正等を理由にクーデターを決行、バイニマラマ司令官が首相として暫定政権を率いることとなった。このクーデターに対しては国際社会、特にオーストラリア、ニュージーランド、EUが批判し、速やかに総選挙を実施して民主主義体制に復帰するよう強く迫った。2009年4月、1997年憲法が廃止。バイニマラマ暫定首相は首相に就任した。
同年7月、バイニマラマ首相は「変化のための戦略的枠組み」と題するロードマップを発表。9月には英連邦から完全に資金を停止された。2013年には新憲法が公布された。バイニマラマは2014年9月の総選挙で首相に再任。2016年には内閣の改造が行われ、外相も兼任することとなった。2018年11月に行われた総選挙では、バイニマラマの首相再任が決定された。
●経済
20世紀の大部分は砂糖産業がフィジー経済を支えてきた。現在では、砂糖産業と年間約84万人の訪問者を迎え入れている観光産業及び海外在住のフィジー人からの送金がフィジー経済の屋台骨を支えている。主な輸出品はミネラルウォーター、砂糖、金、衣類、魚類等である。輸出先は2017年の統計によれば米国が第1位で、オーストラリア、英国、スペイン、ニュージーランドがそれに続いている。また、主要輸入品は金属製鉱産物、機械・輸送機器、工業製品、食料・雑貨品、石油等で輸入先はシンガポールが最大で、ニュージーランド、オーストラリア、中国、韓国が続いている(アジア開発銀行、2017年)。
その他フィジーの概要詳細は、当センターガイドブックをご覧ください。
外務省のページはこちらから