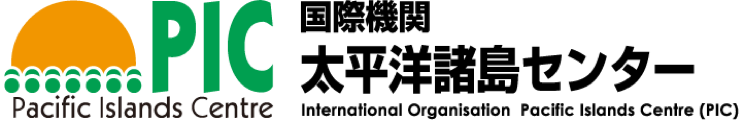クック諸島 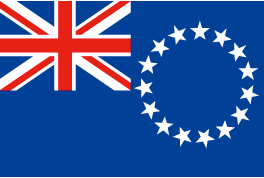
| 正式国名 | クック諸島(Cook Islands) |
|---|---|
| 人口 | 20,200人(2019年、ADB) |
| 民族 | ポリネシア系(クック諸島マオリ族)84%、混血ポリネシア系7% |
| 宗教 | キリスト教97.8% |
| 1人当りGNI | 15,521米ドル(2017年、ADB) |
| 通貨 | ニュージーランドドル(硬貨については独自のものも有する) |
| 面積 | 約240㎢(鹿児島県徳之島とほぼ同じ) |
|---|---|
| 首都 | ラロトンガ島アヴァルア(Avarua) |
| 主要言語 | 英語、マオリ語(共に公用語) |
| 政体 | 立憲君主制 |
| GDP成長率 | −5.9%(2020年、ADB) |
| 電話の国番号 | (682)+(相手先の番号) |

●歴史(第二次世界大戦後)
第2次世界大戦中、アメリカ軍はアイツタキ島とペンリン島に滑走路を建設したが、戦争による影響は殆ど無く、戦後、他の太平洋島嶼国が独立に向けて動き出した際にも、クック諸島は静かなままであった。クック諸島に独立への機運が現れたのは、1960年代に入ってからであり、1965年、内政自治権を獲得してニュージーランドとの自由連合に移行した。

●政治
クック諸島は外交と防衛をニュージーランド(以下NZ)が責任を負う自由連合国である。元首が英国女王エリザベス2世で、首相が政府を率いる。現在は、自由連合協定を締結している関係から、貿易や経済協力の面でNZへの依存は高いものの、1973年にはクック諸島・NZ両首相間の書簡交換で「自由連合」終了権利を確認しており、NZとしてもクック諸島の自立を期待している。現在国連未加盟国ではあるものの、米国やEU、中国を含む27カ国と外交関係を締結している。日本とは2011年3月に国交を締結し、193番目の国として承認された。
●経済
他の島嶼国と同じく、外国市場からの孤立、小規模な国内経済、少ない天然資源、不十分なインフラ、労働人口の減少により経済成長が阻害されてきた。産業はコプラと柑橘果実の輸出が経済を支え、製造業は果実加工、衣料品、ハンドクラフトに限定されている。
貿易収支は、ニュージーランドに住む移民からの仕送りにより、かろうじてその赤字が相殺されている。1980年代、90年代は背伸びをし、政府事業を拡大し、対外負債を累積させたが、90年代半ばからの公務員の大幅削減、政府資産の売却、経済運営の強化、観光促進、債務リストラ協定の締結などによる大胆な改革により窮地を脱した。小規模ながら順調な観光産業と広大な排他的経済水域(EEZ)を基に黒真珠の養殖を中心とした水産業の育成に重点を置いている。経済はその多くをニュージーランド、豪州からの経済援助と両国に住む移民からの仕送りに依存している。
その他詳しい内容は、当センターガイドブックでご紹介しています。
外務省のページはこちらから